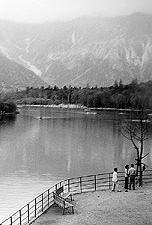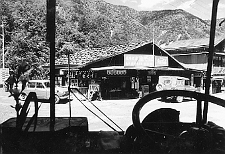穂高から三上山まで
|
目 次 へ |
その1へ・その2
5.これはたまらん!
13時40分、バスプール着。何じゃ?これは。さして広くもない上高地渓谷の、どこからこれだけのひとが出てきたのかと驚く。案内のスピーカーが乗車整理券をとれとわめく。 今晩の白骨温泉の宴会はアウトやな、・・・と、あきらめかけたとき、誰かが、15時50分に、白骨温泉行きが1本だけあるのを探し出してきた。「よし。それや」、もう一度整理券の並び直し。
整理券がとれてしまうと、今度は退屈になる。たしか、カラ松林の中に、遭難慰霊碑があって、そこに尾崎喜八の詩があったぞと、出向いてみる。写真左、遭難慰霊碑。写真右、慰霊碑のレリーフ(穂高連峰の地形を形取っている。手前の谷が上高地渓谷)。
お互い、気の長さを感心し始めたころ、バスは20分遅れでやってくる。そのときの松本行きの乗車番号は、3200番台。これで不満が爆発しないのは、万博で鍛えた忍耐力のたまものか。もっとも爆発さしたところでバスが来るわけでなし、この後、あれだけの人はどうなったのだろう。 やっとの思いで乗ったバスは、大正池畔をあっという間に通過する。これが現代の別れ。 6.白骨温泉 いまの地図を見ると、国道158号から白骨温泉へは立体交差になっているが、そのころはどうだったのか、全く記憶にない。とにかく上高地線から分かれた白骨への道が、かつての上高地線を思わす細い道だったこと。それがぐんぐん高度を上げていくこと。これだけが遠い記憶に残っている。
白骨温泉着。17時半。夕闇迫るころだった。ぷーんと硫黄のにおいが鼻につく。少し坂を上って、白船荘新宅旅館着。 帳場の女将さんが、「ベツヨンゴへご案内」という。それを聞いて、「別館の4階5号室やな」。「4階建ての建物などどこにもなかったぞ」、「どこか別の場所にあるのと違うか」とひそひそ。お婆ちゃんが出てきて「いらっしゃいませ、ご案内いたします」。 ゴカイついでに誤解のないように、上の文章は、昭和40年代半ばの話。現在の様子はこちらをどうぞ。 追記:このあとかなりたってから、理科の教員仲間で、この新宅旅館に泊まった。経緯は忘れたが、そのとき当時のK校長も同道した。さらにその後、何年かして、K校長があの白骨温泉はよかった。もう一度行きたいという。めぼしい連中に声をかけて、宿泊の予約もした。ところが、その旅行を前にして、一行の内の一人T氏がガンで入院してしまった。わしらだけで行くわけにもいかんわな、ということでそのプランはお流れになった。 7.白骨温泉から松本まで。昭和47(1972)年10月11日(水)

目が覚めると雨。昨日一日の好天は貴重だった。
さて、沢渡。昭和30年頃、上高地線のバスが、エンジン冷却のためと称して小休止したところである。左がこのとき1972年現在の写真。右が1969年の写真である。左の写真に写っているトラスブリッジは、昭和30年頃には、木製のつり橋だった。建物と橋の関係は昔ままであるが、これが果たして同じ場所なのか。また、69年に撮った写真が1955年頃と同じ建物なのか。すべてが謎である。
奈川ダム。前回来たときには未完成だった道も、完全舗装成って、快調にとばす。
松本電鉄のホームに無蓋貨車の「ト」が止まっている。難儀な性分で、こういうのを見ると楽しくなる。無蓋貨車では、「トム」というやつが有名だが、「ト」というのは珍しい。貨車は、「ト」が無蓋車、「ワ」が有蓋車、などと形式が定められており、それに積載量の多寡で、「ム・ラ・サ・キ」という記号がつく。「ム」が積載量が少なく、「キ」が大きい。「ム」より小さいやつは、何にもつかない。だから「ト」というのは、「トム」より小さい。珍しい貨車である。京都あたりではほとんど見たことがない。
ホームへ上がって驚いた。片方の扉がぱたんとホーム側へ倒されて、貨車そのものがホームの代わりをしているのである。連結器もついたまま。邪魔になればさっと引き上げるのだろう。誰が考えたのか知らんが、スゴイね、この発想は。XX庁やYY省の役員も、こういう発想を見習らへよ・・・。 
11時15分の電車で松本へ。考えてみれば、この線に乗るのは、昭和30年、初めて西穂高へ来たとき以来。その後は木曽福島へ出るか、飛騨側へ下っていたことになる。駅前で、昼食。乾杯。乾杯は昨夜終わったはずやけど。まあエエ。ゴカイのお婆ちゃんいつまでも元気でな。 8.松本から松本13時13分の名古屋行き。
小降りになったとはいえ、奈良井までは雨。ところが鳥居トンネルを抜けたトタン、驚くような晴天になる。こういう変化が見られるから、旅は面白い。
写真左、木曽福島。夏なら、白装束に杖を持った行者さんでいっぱいだが、いまはひっそり。 |